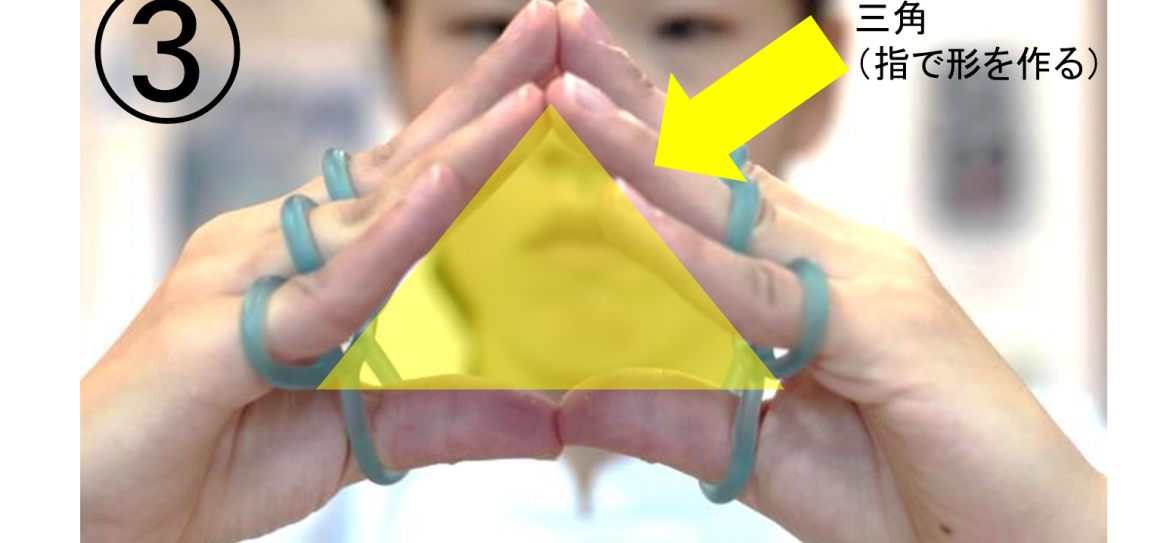あけましておめでとうございます
(新年のあいさつが遅くなってしまい申し訳ございません…(^^;) )
昨年中に賜りました数々のご厚情に、職員一同、心より御礼申し上げます。
今年一年も、‟小さな施設だからできる大きな関わり”をモットーにより良いサービスをご提供できるように努力をして参りますので、さらなるご指導・ご鞭漣を宜しくお願い申し上げます。
さて、1月3日は仕事はじめに八栗寺へ初詣に行ってきました。今年は全員歩いて山頂へ‼
急な坂を登り…(;´・ω・)
1年の感謝と新年の無事と平安を祈願してきました。
ご来光でパワー チャーーージ‼
3年前の今頃少しずつ準備を開始した当施設も
ご利用者やご家族、関係機関の方々の支え
また、新しいスタッフのパワーも加わり
4月には4年目を迎えることができます★
‟やってみたいこと”に‟チャレンジできるように”…
ご利用者が自分らしく過ごせるように…
さんごのおうちに来て「よかった」と言っていただけるように…
スタッフ一同一丸となり頑張ってまいります‼
今後ともさんごのおうちをよろしくお願いいたします。
生活相談員 田中茉衣

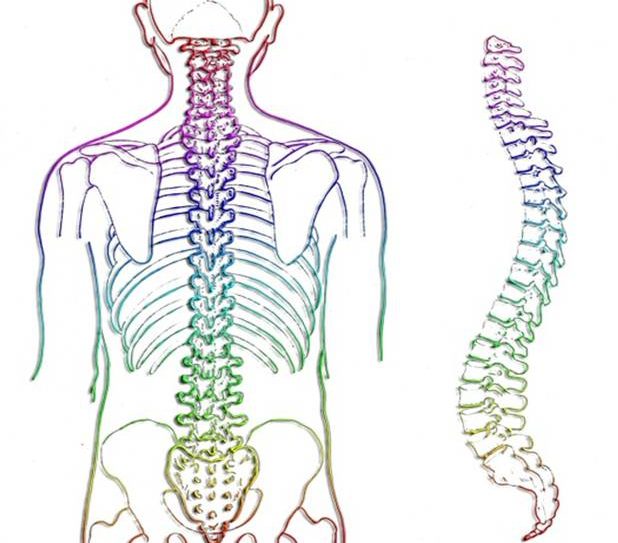


![IMG_3558[1]](http://sangono-ouchi.com/wp-content/uploads/2017/10/IMG_35581-1170x543.jpg)